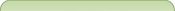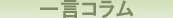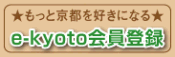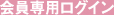今年の秋の土用の丑の日は10月28日です。
毎年10月26日には滝尾神社境内にある三嶋神社祈願所にて、「うなぎ祭」こと「鰻放生...[続きを読む]
今年の秋の土用の丑の日は10月28日です。
毎年10月26日には滝尾神社境内にある三嶋神社祈願所にて、「うなぎ祭」こと「鰻放生...[続きを読む]2024年10月7日(月)の行事一覧
※主催者の都合により、予定・内容が変更される場合がありますので事前にご確認お願いいたします。
玉田神社神幸祭

五穀豊穣を感謝する秋の祭りです。
還幸祭では8つの宮座が役割を分担し、参列します。
おごそかな装束で練り歩くその手に捧げ持たれる神宝!本当座は太刀、
御幣座は御幣、御箸座は箸などを奉じて練り歩きます。
710年に創祀された古式ゆかしい神社です。
大地から恵みをいただいている…日々の暮らしに感謝、です。
| ■場 所: | 玉田神社 |
| ■期 間: | 2023年10/7(土) |
| ■時 間: | 例祭:13時~、神幸祭:18時~ |
| ■アクセス: | 近鉄京都線「大久保」駅より京阪宇治交通バス「久御山町役場前」 |
| ■お問合せ: | 075-631-0307 |
| ■詳細ページ: | 玉田神社公式ホームページ |
季節の光景...源光庵・ススキ<薄>

春は常照寺の桜と光悦寺の菜の花、秋は源光庵のすすきが美しい洛北・鷹ヶ峰です。
すっかり涼しくなった秋風がさらさらとすすきの穂を巻き上げていきます。
芸術家、本阿弥光悦が創作活動の拠点を置いたという鷹ヶ峰。源光庵には「悟りの窓」、「迷いの窓」があり、それぞれからお庭を眺めることができます。
物思いにふける事もままならない程の灼熱の夏もいつしか過ぎ去り、 ゆっくりとわが道を振り返られる季節になりました。
これらの窓からあなたは何を見ますか?
| ■場 所: | 源光庵、常照寺、光悦寺 |
| ■アクセス: | 地下鉄「北大路」駅より市バス北1「鷹峯源光庵前」 |
| ■お問合せ: | 常照寺:075-492-6775 光悦寺:075-491-1399 源光庵:075-492-1858 |
| ■詳細ページ: | 源光庵公式サイト 常照寺公式サイト |